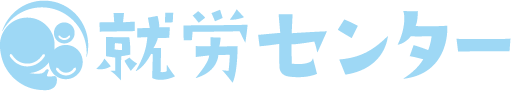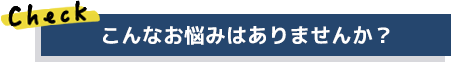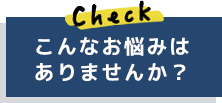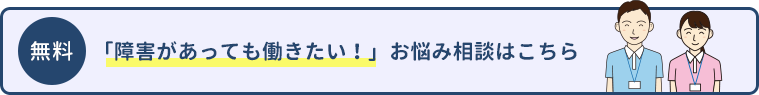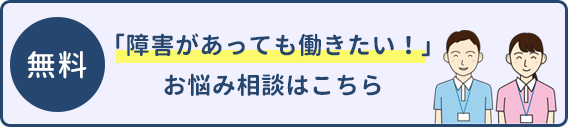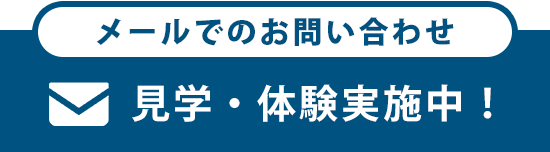- 仕事が長続きしないのは発達障害のせい?
- なぜ発達障害だと仕事が続かないの?
- 発達障害に向いている仕事は?
- 発達障害でも仕事を長続きさせる方法を知りたい
この記事ではこれらの疑問について、詳しく解説します。
発達障害のある方の中には、職場での対人関係やミスの多さ、環境への適応の難しさなどから、仕事が続かないことに悩んでいる方が少なくありません。
繰り返される転職や自信の喪失に、「もう働くこと自体が難しいのかも」と感じてしまうこともあるでしょう。
本記事では、発達障害と仕事が続かない理由について深掘りしつつ、特性を活かせる仕事の選び方や、働き方の工夫、活用できる支援制度について詳しく解説します。
自分らしく、無理のないペースで働き続けていくために、ぜひ最後までお読みください。
目次
発達障害だと仕事が続かない理由

発達障害のある方が仕事を続ける上で直面する困難には、特性に起因するさまざまな要因があります。
まずは、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD(学習障害)の3つの特性に焦点を当て、それぞれ仕事の継続にどのような影響を及ぼすのかを詳しく解説します。
ASD(自閉スペクトラム症)
ASDの特性を持つ方は、以下のような困難を理由に仕事が続かないことがあります。
- 対人関係の難しさ
非言語的なコミュニケーション(表情や身振り)を読み取ることが難しく、職場での人間関係にストレスを感じやすいです。 - 臨機応変な対応の難しさ
予期しない業務の変更や環境の変化に適応するのが難しく、ストレスの原因となります。 - 感覚過敏
音や光、匂いなどに敏感で、職場環境によっては集中力が低下することがあります。
これらの特性が原因で、職場でのストレスが蓄積し、結果として仕事を続けることが難しくなるケースがあります。
ADHD(注意欠如多動症)
ADHDの特性を持つ方は、以下のような課題に直面することがあります。
- 注意力の持続が困難
長時間の集中が難しく、ミスが増える傾向があります。 - 衝動性や多動
思いついたことをすぐに行動に移しやすく、業務の優先順位がわからなくなることがあります。 - 時間管理の難しさ
スケジュール通りに行動するのが難しく、遅刻や締切の遅れが生じやすいです。
これらの特性が職場での評価に影響し、自信を喪失することで離職につながることがあります。
LD(学習障害)
LDの特性を持つ方は、特定の学習領域に困難を抱えることがあります。
- 読み書きの困難
文書の読み取りや書くことに時間がかかり、業務効率が低下することがあります。 - 計算の難しさ
数値の処理や計算が苦手で、特に経理や販売などの業務でミスが生じやすいです。 - 実行機能の課題
指示や手順を理解するのが難しく、業務の習得に時間がかかることがあります。
これらの困難が積み重なることで、職場での評価が下がり、仕事を続けることが難しくなる場合があります。
発達障害の特性は個人差が大きく、すべての方に当てはまるわけではありません。
しかし、自分の特性を理解し、適切な支援や配慮を受けることで仕事を続けることが可能になります。次は、発達障害の特性を活かせる仕事について詳しく解説します。
発達障害の特性を活かせる仕事

発達障害のある方は「できないこと」ではなく、「活かせる特性」に目を向けてみましょう。
ここではASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD(学習障害)それぞれの特性と、向いている仕事をご紹介します。
ASDの特性と向いている仕事
ASD(自閉スペクトラム症)の方には、以下のような特性があります。
- 規則的・反復的な作業が得意
- 細部へのこだわりが強く、注意深い
- 一人で黙々と作業することを好む
こうした特性を活かせる仕事の一例を紹介します。
| 仕事名 | 特徴・理由 |
|---|---|
| データ入力 | 一人で集中して行える反復作業で、細かいミスに注意できる人に向いています。 |
| 仕分け・検品 | 作業手順が決まっており、黙々と取り組むことが得意な方に適しています。 |
| 清掃作業 | ルーティン作業が多く、静かな環境で働ける職場もあるためストレスが少ないです。 |
| 経理事務 | 細かな数字を扱う仕事で、几帳面な人やコツコツ作業が好きな人に向いています。 |
ASDの方には、「予測可能な業務」「静かな環境」「一人で取り組める状況」が安心材料となります。
ADHDの特性と向いている仕事
ADHD(注意欠如多動症)の方には、次のような特性が見られます。
- エネルギーがあり、じっとしているより動き回る方が好き
- アイデアを次々に出せる柔軟な発想力がある
- 好きなことへの集中力がとても高いが、興味関心が移り変わりやすい
このような特性を活かせる仕事を紹介します。
| 仕事名 | 特徴・理由 |
|---|---|
| 営業 | ADHDは新規開拓営業・歩合制営業などで、行動力や対人スキルを活かしやすいです。 |
| 画像加工・簡単なデザイン補助 | アプリなどのツールを使ったチラシやSNS投稿の素材作りなど。創造力と試行錯誤する力を発揮しやすいです。 |
| 動画編集 | 短い動画のカットやテロップ入れなどは、創造性と集中力を活かしやすいでしょう。 |
| イラストレーター | 在宅でも取り組みやすく、自由な発想で個性的な作品を生み出す力があります。 |
ただし、注意点もあります。締め切り管理やスケジュール調整が苦手になりやすいので、アプリを活用したり、協力的なパートナーを見つけるのもおすすめです。
LDの特性と向いている仕事
LD(学習障害)の方は、以下のような特性を持つことがあります。
- 読み書きや計算など、特定の学習に困難がある
- 目に入った情報の位置や距離感を把握する力が高い人も多い
- 手先が器用な人も多い
たとえば、読字障害と書字障害、算数障害の人では持っている特徴が異なります。
- 読字障害
文字の形や読み方の認識が苦手、読めても内容の理解が難しい - 書字障害
文字を書くことが苦手、似ている文字を間違えやすい - 算数障害
簡単な計算が苦手、図形やグラフ問題の理解が難しい
同じLDでも文字が読める人もいれば、読むことが苦手な人もいます。次のような仕事から自分に合いそうなものを探してみてください。
| 仕事名 | 特徴・理由 |
|---|---|
| 軽作業(袋詰めなど) | 手順が分かりやすく、文字の理解をあまり必要としない仕事です。 |
| 手工芸・ものづくり | 手先の器用さや集中力を活かせるので、特に読字障害の人に向いている仕事です。 |
| データ入力 | パソコンでコツコツ入力する作業は、書字障害のある人に向いています。 |
| 調理関係 | 味付けや盛り付けなど感性を表現できる業務です。クリエイティブなことが得意な算数障害の人に向いています。 |
LDの方は「体を使って作業できる仕事」などが適しているでしょう。
発達障害の方によくある仕事での困り事

発達障害のある方は、それぞれの特性によって仕事の中でつまずきやすい場面があります。よく聞かれる悩みを具体的に取り上げ、どのような背景や特性が関係しているのかを解説します。
- ミスばかりを繰り返しやすい
- 指示があいまいだと動けなくなる
- 雑談などのコミュニケーションが苦手に感じる
- 仕事をなかなか覚えられない
- 転職を繰り返す癖がついた
ミスばかりを繰り返しやすい
発達障害の方は注意力のコントロールが苦手な人もいます。
特にADHDの人はケアレスミスや確認不足などを繰り返しやすいです。周囲の人から「だらしない」「仕事ができない」と誤解されることもあります。
指示があいまいだと動けなくなる
ASDの方は「曖昧な言葉や状況」に強い苦手意識があります。
「適当に」や「臨機応変に」といった指示ではどう動けばいいかわからなくなることがあります。結果として、手が止まり「指示待ち」になりやすいのです。
雑談などのコミュニケーションが苦手に感じる
発達障害の方は、何気ない会話や職場の雑談に苦手意識を持つ人も多いです。
たとえばASDの方は「空気を読む」「相手の感情を察する」ことが難しい特性があります。ADHDの方は「話しすぎてしまう」「話が逸れる」傾向があるのです。
仕事をなかなか覚えられない
新しい作業を覚えるのに時間がかかる人も多いです。
たとえばLDの方は、言葉や数字の情報処理に困難を感じやすく、マニュアルを読んでも理解しづらいことがあります。また、ADHDやASDの方も、新しい状況への適応に時間がかかることがあります。
転職を繰り返す癖がついた
「仕事が合わない」と感じ、結果的に転職を繰り返す方も多いです。
業務が合っていないこともあれば、人間関係や業務の進め方で挫折してしまうこともあります。気づけば履歴書が転職歴だらけになり、「また続かないかも」と自己否定につながることもあるのです。
仕事が長続きしないことによるデメリット

発達障害のある方にとって、「仕事が続かないこと」は珍しいことではありません。
ただし、短期間での離職が続くと、経済的・精神的・社会的な面でさまざまな影響が出る可能性があります。ここでは、考えられる5つのデメリットを紹介します。
- 経済面に不安を感じやすくなる
- やめ癖がついてしまう
- 社会的な信用が低下する
- 自信がなくなる
- スキルアップが難しくなる
経済面に不安を感じやすくなる
仕事が続かないことで収入が安定せず、将来への不安が強まる人も多いです。
貯金ができず、急な支出に対応できない場面も増えます。一人暮らしをしたくても、実家に戻ることになる方も多いのです。
経済面に不安を感じると、メンタルも不安定になりやすく悪循環に陥りやすくなるでしょう。
やめ癖がついてしまう
長続きしないと、仕事をやめる癖がつきやすくなります。
合わない職場で我慢し続ける必要はないですが、次の転職時に「また辞めたらどうしよう」と不安がつきまといますし、「辞めた自分を責める」思考パターンが習慣化してしまうこともあります。
社会的な信用が低下する
職を転々としていると、履歴書や面接での印象が悪くなることもあります。
ただし、障害があることを伝えた上でこの先できる工夫や自己理解を深めたことを伝えると印象も変わるでしょう。
たとえば、発達障害による配慮が必要だったことを就労支援機関を通して丁寧に説明すれば、理解を得られる企業もあります。
自信がなくなる
仕事がうまくいかない経験が積み重なると、「どうせまた失敗する」と思いやすくなります。「仕事が続かない自分はダメだ」と自己否定しやすくなるのです。
自己否定がさらに仕事への苦手意識を強めてしまう悪循環に陥ることもあります。
スキルアップが難しくなる
短期間で退職を繰り返すと、スキルや経験が積み上がりにくくなります。「前職の仕事が次に活かせない」という状況にも陥りがちです。
キャリアの幅が広がらず、選べる仕事が限られることもあります。
発達障害の方が仕事を長続きさせる方法

発達障害をお持ちの方が仕事を長く続けるために、次に紹介する方法を少しずつはじめてみましょう。
自己理解を深める
仕事を長く続けるためには、自分の得意・不得意を正しく把握することが欠かせません。自分の特性を理解することで、無理のない働き方を選べるようになります。
たとえば、ASDの方は、静かな環境での黙々とした作業が合っていることが多いです。ADHDの方は、動きのある仕事や変化に富んだ職場が向いていることがあります。
自己理解を深めるためには、今まで辞めた職場環境や仕事内容の「よかったところ」「疲れやすかったところ」などをまとめてみるといいでしょう。ほかにも、このあと紹介する方法を組み合わせて、自己理解を深めてみてくださいね。
頼れるツールを活用する
苦手なことを補うためのツールや工夫を取り入れれば、仕事上の困りごとを軽減できます。
たとえば、タスク管理が苦手な方は、スマートフォンのリマインダー機能や、ToDoリストアプリ(例:Google Keep、Todoistなど)が役立つでしょう。
また、メモや録音しながら業務を行い、視覚的にスケジュールを管理するホワイトボードを使う方法も有効です。ツールの活用により、ミスや忘れ物を防げるだけでなく、自分に自信を持つきっかけにもつながります。
ストレス対処法を身につける
ストレスとうまく付き合い、退職のリスクを防ぐことが重要です。具体的には、以下のような方法があります。
- 深呼吸や軽いストレッチでリラックスする
- 小さな成功体験を記録し、自分を認める習慣を持つ
- 1日の終わりに「よかったこと」を3つ書き出す
また、ストレスを感じやすい場面を振り返り、対応をあらかじめ考えておくのも効果的です。心の余裕を保つ工夫は、働き続けることに役立ちます。
困りごとを減らす関わり方を工夫する
困りごとを減らすために、コミュニケーション面で工夫してみましょう。
たとえば、あいまいな指示が苦手なら「〇〇は△△という意味で合っていますか?」と確認する習慣をつけるのはいかがでしょうか。また、言葉だけでの指示では理解しづらいときは「間違えないようにメールで送っていただけますか?」とお願いしてみるのも有効です。
伝えるのは勇気が必要ですが、適切に伝えることは誤解やストレスを減らすことにつながります。自分の「働きやすさ」の一歩として、ぜひ意識してみてください。
仕事が続かないときに見直すべきポイント
就職や転職するときは意気込んでいても、仕事が続かないこともあります。うまくいかないと感じたときに見直すべきポイントを4つ紹介します。
- 自分の特性の把握
- 働き方の選択肢
- 職種や環境の向き不向き
- 専門家など相談先の有無
自分の特性の把握
仕事が続かない背景には、自分の特性に合わない働き方を選んでいる可能性があります。
発達障害の方には「段取りが苦手」「注意がそれやすい」「空気を読むのが難しい」など、特性に応じた困りごとが現れやすいです。しかし、特性にも個人差があります。
「自分はどんなときに調子がよく、どんな場面で苦手を感じるか」を整理しておくことで、今後の働き方の選択に役立てましょう。
働き方の選択肢
働き方にはフルタイムの正社員以外にも多様な選択肢があるので、自分の特性に合った形を選びましょう。
たとえば、体調や集中力に波がある方は短時間勤務やフレックスタイム制度がある職場が適しています。また、対人関係の負担が大きい方は在宅勤務や一人作業の多い職場が能力を発揮しやすいこともあるのです。
体調や環境の変化に合わせて働き方を見直すことも、仕事を続けるうえで大切な視点です。
職種や環境の向き不向き
どんなに努力しても、仕事内容や職場環境が合わないと働き続けることは難しくなります。
自分の特性に合った職種・作業内容であれば、疲れにくく、ストレスも感じにくくなるのです。職場の理解やサポート体制も、働きやすさを大きく左右させます。
「向いていないのでは」と感じたら、自分を責めるのではなく、仕事との相性を見直してみましょう。
専門家など相談先の有無
自分ひとりで抱え込まず、専門機関に相談しましょう。発達障害に関する知識を持つ支援機関では、適職探しや職場への配慮の伝え方など具体的なアドバイスを受けられます。
主な相談先は次の通りです。
| 相談先 | サポート内容 |
|---|---|
| ハローワーク | 障害者向けの求人紹介、職業相談、職場実習など。「障害者関連窓口」は精神障害者手帳がなくても利用可。 |
| 障害者就業・生活支援センター | 職場定着支援、福祉サービスとの連携など。 |
| 地域障害者職業センター | 障害者に対する専門的な職業リハビリテーションや職業相談など。 |
| 就労移行支援事業所 | 就職に向けたスキル訓練、ビジネスマナー講座、職場実習、求人紹介などを提供など。 |
| 就労継続支援A型事業所 | 雇用契約を結びながら軽作業等に従事し、一般就労を目指すサポートなど。 |
| 就労継続支援B型事業所 | 雇用契約なしで、自分のペースで作業訓練を行うなど。 |
「就労継続支援B型事業所」は、体調や精神面に不安がある方でも自分のペースで「働くこと」に慣れていける場所です。
次の章では、就労継続支援事業所の特徴やメリットについて詳しく解説していきます。
自分のペースで働きたい方は就労継続支援を利用しよう

就労継続支援の概要や、A型・B型の違い、事業所の選び方についてご紹介します。
就労継続支援とは
就労継続支援とは、障害や体調の面で一般企業で働くことが難しい方に向けて、仕事の機会を提供する福祉サービスです。
厚生労働省による障害福祉サービスのひとつで、就労経験を積みながら生活リズムや職業スキルを整えることを目的としています。
参考:厚生労働省 令和4年度「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス」
A型とB型の違い
就労継続支援にはA型とB型の2種類があります。
| A型 | B型 | |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 工賃 | 最低賃金以上が保障される | 作業に応じた工賃が支払われる |
| 利用対象者 | 一般就労がある程度可能な状態 | 就労に対して工夫が必要な状態 |
| 作業難易度 | 比較的高い | 難易度の低い作業が多い |
| 勤務時間・日数 | フルタイムや短時間勤務 | 自由度が高く柔軟に調整できる |
A型は雇用契約があるため、企業就労に近い形で働きたい方に向いています。一方で、B型は「まずは自分のペースではじめたい」という方にぴったりです。
B型は体力に自信がない方や、決まった時間に働くことが不安な方も無理なく参加できます。週に1〜2回の短時間からスタートすることも可能なので、自分のペースで働き方を整えられます。
参考:厚生労働省 令和4年度「障害者福祉施設における就労支援の概要」
自分に合う就労継続支援事業所を選ぼう
発達障害の方で就職先や日中の活動場所にお悩みでしたら、就労継続支援B型事業所が適しているかもしれません。
愛知県にある就労センターは、就労継続支援B型事業所として13年の運営実績があります。
週1回半日から利用でき、軽作業やパソコン作業など、無理なく取り組める作業を数多くご用意しており、一人ひとりに寄り添った支援体制が整っています。
通所する利用者さんの60%以上が発達障害(ASD、ADHD、LD)や精神疾患をお持ちで、自分のペースで働きながら一般就労に進んだ方も数多くいらっしゃいます。一般企業への就職を希望される方も、ぜひ一度見学にお越しください。
発達障害についてよくある質問
Q.発達障害の二次障害とは?
発達障害の方がうつや不安障害になることを「二次障害」と言います。特性による困難が長く続くことで、強いストレスや挫折感が積み重なるためです。
たとえば「努力しても報われない」という経験が、自己否定感や対人不安につながるケースもあります。
二次障害は本人の生活や就労に大きく影響するため、早めの気づきと支援が重要です。
Q.発達障害だけでなく知的レベルも仕事に影響しますか?
知的能力の違いも仕事への適応に関係します。
軽度の知的障害がある方は、作業理解やスピードに配慮が必要となる人もいるでしょう。ともに働く人は理解しやすい説明や環境の工夫が重要になります。
支援機関では知的レベルに応じた支援が行われることも多いため、自分に合った就労環境を見つけやすいです。
Q.診断がついていないと就労継続支援は利用できませんか?
精神疾患や発達障害、知的障害、身体障害、難病の方であれば利用可能です。また、医師の意見書があれば、利用可能な事業所もあります。
一般的には以下の条件に当てはまり、利用可能と判断された人であれば利用可能です。
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用が難しい方
- 50歳以上、または障害基礎年金1級を受給者
- 就労移行支援事業者の評価で就労継続支援B型事業所を利用が適切と判断された方
わかりにくいルールも多いと思いますので、ご不明な点等ございましたらまずは一度就労センターにご相談ください。
まとめ
発達障害の方が仕事を続けられないときの対処法や向いている仕事、福祉サービスなどをご紹介しました。
特に就労継続支援B型事業所は、自分の能力に合わせた作業や柔軟な勤務時間を選べるため、ストレスを軽減しやすくなります。自己理解を深め、自分に合った支援を受けることが長期的な就労に繋がるでしょう。
今回の内容が、発達障害で仕事が続かない方の参考になれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

心理学の専門家として精神科病院や心療内科クリニック、児童発達支援事業所の勤務を経て、現在はフリーのカウンセラー、児童精神科の心理士として活動中。障害領域における知識・支援技法を持ち合わせている。

2014年に行政書士資格取得後、行政書士法人にて研鑽を積み、2016年から障害福祉分野に注力。福祉事業所には欠かせない都道府県・市町村への各種申請件数は100件以上。
また、福祉施策調査を実施し、障害福祉事業所に対し、運営提言も行っている。「行政書士ありもと法律事務所」の代表行政書士でもある。