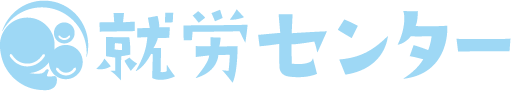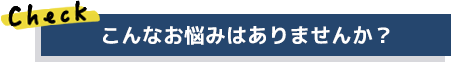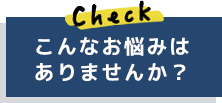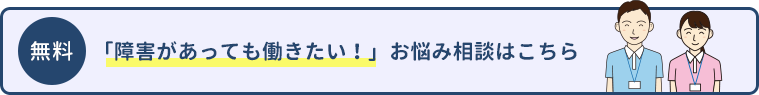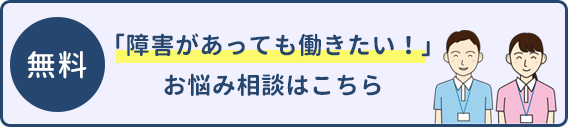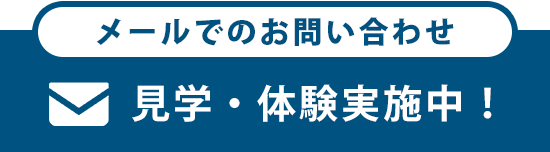- 精神障害と知的障害って何が違うの?
- 精神障害と知的障害の特徴や原因は?
- 精神障害者や知的障害者への対応や接し方を知りたい
この記事ではこれらの疑問について、詳しく解説します。
突然ですが、「精神障害と知的障害の違いは?」と聞かれたら、どのように答えますか?
「精神障害は精神の障害で、知的障害は知的な障害?」
「精神障害はメンタルの病気で、知的障害は知能の発達が遅れている状態?」
「精神障害は病気だから治るけど、知的障害は障害だから治らない?」
それぞれの障害については、なんとなく知ってはいるものの、違いの説明ともなるとなかなか難しいのではないでしょうか。
精神障害も知的障害も、主な症状や特徴については知られていますが、実際には個人差が大きく症状はさまざまです。さらに障害が重複している場合は複雑になります。
そこで今回は、精神障害と知的障害の症状や特徴の違い、接し方のポイントや支援制度等について解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
精神障害・知的障害の原因、症状の違い
ここでは、精神障害と知的障害がそれぞれどういう障害なのかを見ていきましょう。
精神障害とは
実は、精神障害についての定義は統一されていません。法律によって表現の違いがあるのです。
精神保健福祉法では「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存性、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの」としていますが、医師や専門家によって診断が異なる場合があるため、明確に定義づけられていないというのが実情です。
障害者基本法においての精神障害者は、「精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」としています。
参考:日本精神保健福祉士協会「法律における精神障害の定義」
精神障害の原因
精神障害(精神疾患)の原因は、心因性、内因性、外因性に分けて考えられています。
| 心因性 | 心理的原因とも言われ、悩み、ストレスなどの心理的な影響によるもの。 |
| 外因性 | 脳梗塞や脳炎などの疾患、外傷などによって起こった、脳の器質的変化によるもの。 |
| 内因性 | 心因性、外因性にあてはまらない、特定できないもの。(性格や遺伝性が関与していると考えられている) |
精神障害の種類と症状
代表的な精神障害(精神疾患)の主な症状は、以下の通りです。
統合失調症
思考や感情がまとまらない状態が続き、100人に1人程度の割合で発症していますが、原因については解明されていません。
- 幻覚、妄想(陽性症状)
- 意欲・集中力の低下、引きこもり、疲れやすい、清潔保持の欠如、感情の起伏が乏しくなる(陰性症状)
- 記憶力、判断力、注意力の低下(認知機能障害)
気分障害
気分が高揚したり落ち込んだりする変動が、普通のレベルを超えて一定期間続き、日常生活に支障をきたす状態を指します。
- 気分が強く落ち込む、意欲の低下、思考の低下、死にたい気持ちになる(うつ状態)
- 過剰な高揚感、怒りやすくなったり、極端な浪費や延々と喋りつづける、働き続ける(躁状態)
- うつ状態だけのもの(うつ病)
- うつ状態と躁状態を一定期間繰り返すもの(双極性障害)
てんかん
脳のなんらかの異常によって、脳全体ないし一部で発生する過剰な電気的興奮によって、発作を繰り返します。原因が明らかではない「特発性てんかん」、外傷や脳炎、脳梗塞等の損傷によって起こる「症候性てんかん」、「分類不能なてんかん」に分かれます。
- けいれんを伴う意識の消失、唇・爪・舌などが青紫色に変色するチアノーゼの症状などが起こる(強直間代発作)
- 部分発作が起こる。意識を保ったまま、身体の部分的に発作が起こる単純部分発作と、意識が消失して動作が停止し、口をもぐもぐ動かす等の複雑部分発作に分かれる
依存症
特定の物質や行為をやめたいのに、やめることができない状態のことをいいます。代表的なものではアルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症があります。
- 飲酒の量がコントロールできない。飲酒への強い欲求。アルコールが切れた時の離脱症状(※)が出る(アルコール依存症)
- 使用する薬物の適切な量をコントロールできない。薬物を使用したい強い欲求。薬物が切れた時の離脱症状が出る(薬物依存症)
- ギャンブルの頻度、ギャンブルに使う金額のコントロールができない。ギャンブルで負けた金額を取り戻すためにギャンブルを繰り返す(ギャンブル依存症)
※離脱症状とはアルコールや服薬中の薬など、依存しているものを減量したり、中止したときに現れる身体・精神症状を指します。(イライラする、不安になる、うつ状態、震え、発汗、吐き気など。)
高次脳機能障害
頭部外傷や脳梗塞等の疾患により、脳にダメージを受けたことで認知障害・行動障害が起きます。
- 新しい事が覚えられない、すぐ忘れてしまう、同じ質問を繰り返す(記憶障害)
- 集中力が途切れたり、注意散漫になって、ミスを起こしやすい(注意障害)
- 計画を立てて実行したり、順序立てて効率よく物事を進めることができない(遂行機能障害)
- すぐにイライラしたり、粗暴になる。我慢ができない(社会的行動障害)
- 症状がでていることに気づかず、周囲とトラブルになる(病識欠如)
強迫性障害
不安や恐怖を引き起こす考え(強迫観念)が頭から離れず、それを打ち消すための行為(強迫行為)で日常生活に支障をきたします。
- 手がばい菌で汚染されていると感じ、何度も手洗いをする
- 戸締りがきちんとできたか不安になり、何度も施錠確認する
知的障害とは
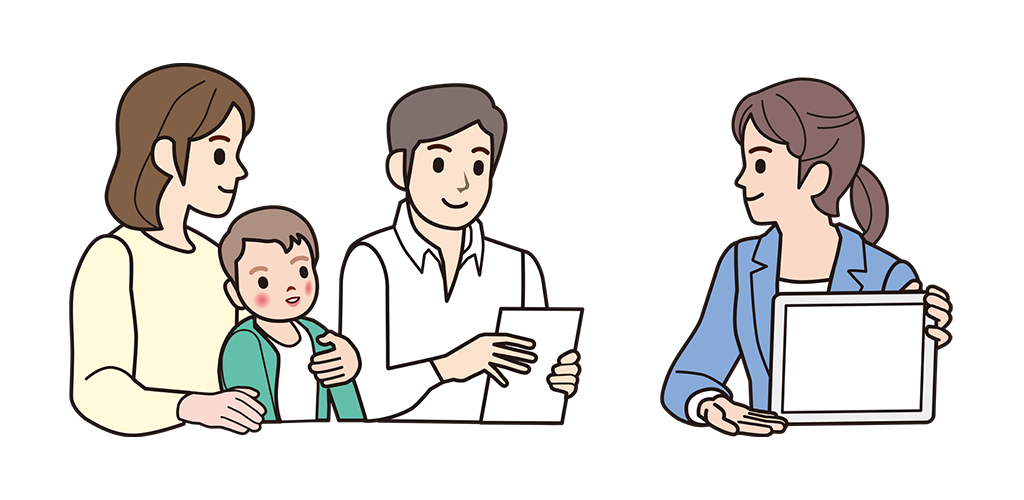
厚生労働省によると、知的障害とは「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」としています。
乳幼児健診や就学前健診でなんらかの発達の遅れが発見され、検査を受けることで診断されることが多いようです。
参考:厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査:調査の結果」
知的障害の原因
知的障害の原因については不明な場合が多いですが、主な要因として3つに分類されています。
| 病的要因 | 病気(染色体異常・感染症・遺伝子疾患等)や脳損傷によるもの。※脳性まひ・ダウン症・てんかん等 |
| 生理的要因 | はっきりとした原因が分からないもの。 |
| 心理社会的要因 | 養育者からの重度のネグレクトや虐待など、不適切な養育環境によるもの。 |
知的障害の分類、症状
知的障害の診断には、主に「田中ビネー知能検査V」「新版K式発達検査」「ウェクスラー式知能検査」といった検査が使われています。
田中ビネー知能検査V
「思考」「言語」「知覚」「数量」「記憶」で構成された検査で、どの年齢の知能レベルに到達できているかが分かりやすい。被験者と検査者1対1で、計算、パズル、図形問題、単語の説明、物語の理解などの問題を解答する。(対象:2歳~大人、検査時間:30~60分程度)
新版K式発達検査
「姿勢・運動」「認知・適応」「言語・社会」の3つの領域で、実年齢の発達水準とどのくらい差があるのか評価する検査。被験者と検査者1対1で行う。検査者は、質問でのやり取りや行動観察、ケンケン、片足たち等の身体面での発達検査を実施して、総合的に評価する。(対象:0歳~大人、検査時間30~40分程度)
ウェクスラー式知能検査
言語理解、流動性推理、視覚空間、作動記憶、処理速度の5つの領域で評価する。知能指数だけではなく、得意、不得意が明確にできる。被験者と検査者1対1で行い、説明、記号探し、計算、パズル、絵の完成問題などを解答する。(検査時間60分~)
知的障害の各区分と状態については、以下の通りです。
| 区分 | IQ(知能指数) 平均を100とする |
状態 |
|---|---|---|
| 最重度知的障害 | ~20 |
|
| 重度知的障害 | 21~35 |
|
| 中度知的障害 | 36~50 |
|
| 軽度知的障害 | 51~70 |
|
参考:厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査:調査の結果」
知的障害・精神障害・発達障害の関連性
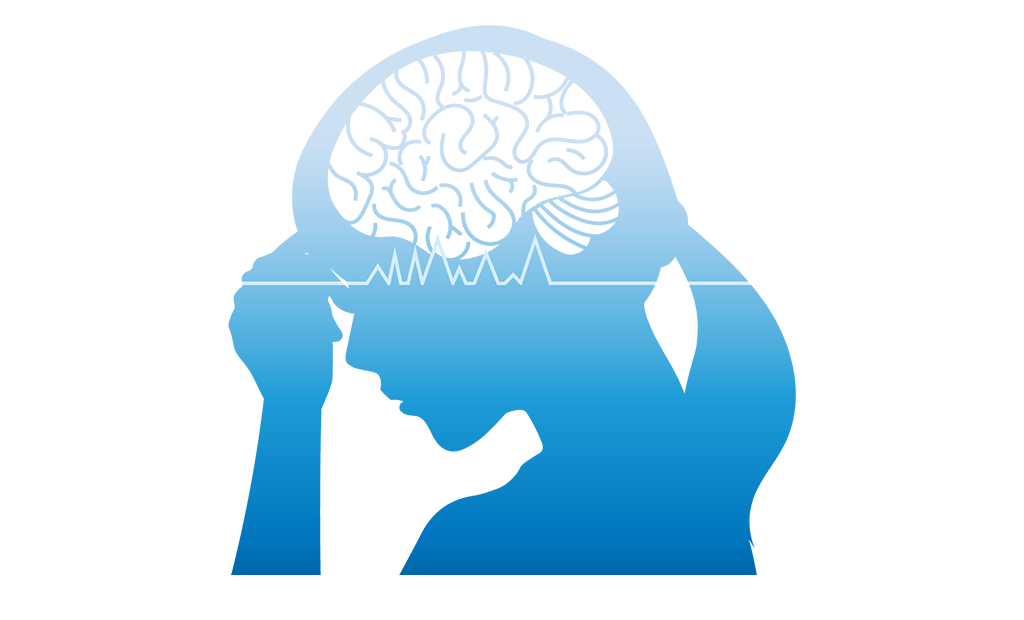
精神保健福祉法において、知的障害は精神障害に含まれて定義されていますが、発達障害も分類上は精神障害に含まれています(障害者基本法・障害者自立支援法)。つまり、一見すると別々の障害ではありますが、広義では同じ精神障害の分類ということになります。
ここでは知的障害・精神障害・発達障害がそれぞれどのように関連性があるのか見てみましょう。
知的障害と精神障害
知的障害と精神障害の関連性では、知的障害のある人がてんかんといった精神障害を併発するケースがあります。また、統合失調症やうつ病の人が、認知機能によって、検査上でIQの数字が下がることもあります。
知的障害と発達障害
発達障害とは「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。
参考:厚生労働省「発達障害の理解のために」
基本的にアスペルガー症候群、高機能自閉症、学習障害(LD)は知的障害を伴いませんが、アスペルガー症候群・高機能自閉症以外の自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害(ADHD)は、知的障害も重複している場合があります。
アメリカ精神医学会による精神疾患診断基準・診断分類のDSMでは、知的障害は発達障害「神経発達症群/神経発達障害群」に含まれています。
精神障害と発達障害
発達障害は精神障害の分類になります。よくあるケースでは、発達障害の二次障害として、うつ病、不安障害、適応障害等の併発があります。
過度な不安や緊張感が持続し、日常生活に支障をきたす状態。
特定のストレス要因によって、抑うつ気分、不眠、不安感等が現れ、日常生活に支障をきたす状態。
精神障害・知的障害の特徴と配慮するポイント
精神障害と知的障害の症状について理解したうえで、接し方についてはどのように配慮すればよいのでしょうか。ここでは特徴をふまえてまとめました。
精神障害の特徴
精神障害のある人の主な特徴には、次のようなものが挙げられます。(★発達障害含む)
- 疲れやすい
- 判断力が低下
- 消極的になりやすい
- 注意力が途切れる
- 不安になりやすい
- 集中力が続かない
- コミュニケーションが上手くいかない(★)
- 周囲の空気が読めない(★)
- 見通しの立たないことが苦手(★)
- におい、気温、音などの感覚過敏(★)
接し方や配慮するポイント
| 接し方 | 配慮するポイント | |
|---|---|---|
| 職場編 | 周囲の同僚と同じように自然な雰囲気で接する |
|
| 体調を把握してスケジュールを調整する |
|
|
| 分かりやすい指示を出す |
|
|
| 困っている様子を察知したら声をかける |
|
|
| 学校編 | 基本的には周囲と同じように接し、体調が悪そうなときは見守る |
|
| 困っている様子を察知したら声をかける |
|
|
| 学習環境を整える |
|
|
| 予定表を提示する |
|
知的障害の特徴
知的障害のある人の主な特徴には、次のようなものが挙げられます。
- 抽象的なことの理解が難しい
- 複雑な状況や事情、会話の理解が難しい
- 自分の考えをうまく伝えることが難しい
- 手先の細やかな動きが難しい
接し方や配慮するポイント
| 接し方 | 配慮するポイント | |
|---|---|---|
| 職場編 | 年齢に応じた態度で接し、ゆっくりと穏やかに話かける |
|
| 指示は短く明瞭に伝える |
|
|
| 報告・連絡・相談を促す |
|
|
| イラストやマークなどを利用する |
|
|
| 学校編 | ゆっくりと穏やかに話かける |
|
| 集団行動の際は細やかに声かけをする |
|
|
| 分かりやすい言葉で伝えたり、絵カードを取り入れる |
|
|
| 学習しやすい環境を整える |
|
精神障害や知的障害の方に交付される障害者手帳
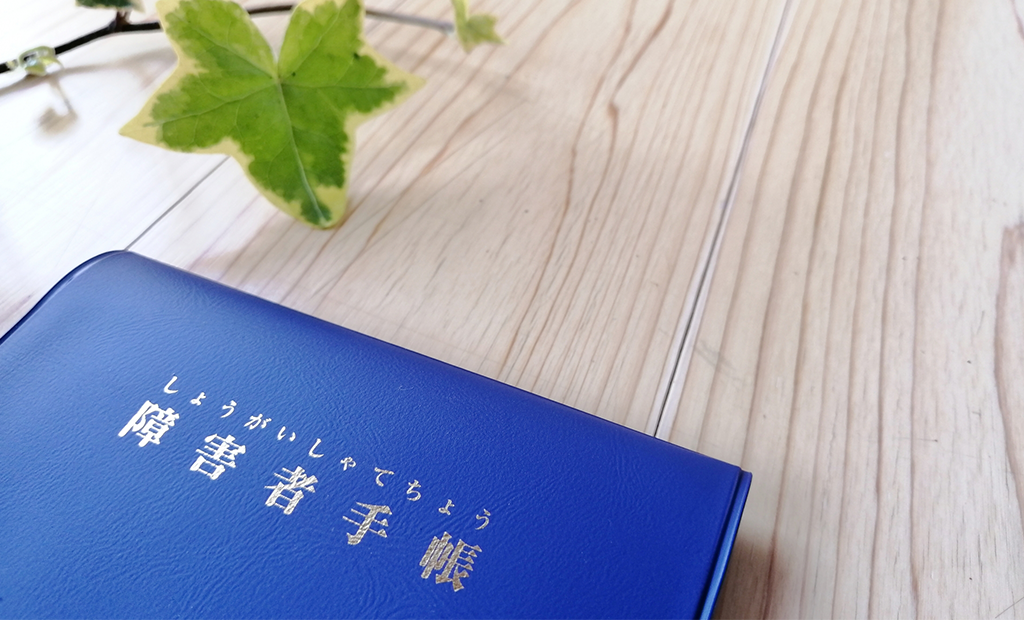
障害者手帳には、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、身体障害者手帳の3種類があります。精神障害と知的障害の両方の障害がある人は、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の両方の手帳が取得できます。
障害者手帳の所持によって、各自治体や民間事業者のサービスが受けられますが、種類や区分によって受けられるサービスの違いがあります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害がある人に交付される手帳です。申請には初診日から6か月以上経った時点の診断書、又は精神障害で年金を受給している場合は、年金証書の写しなどが必要です。
| 申請窓口 | 各市町村担当課 |
| 有効期限 | 2年間(更新手続きが必要) |
| 区分 ※数字が小さい区分ほど重度 |
1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級 精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 受けられるサービス |
|
<参考>
厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」
愛知県「精神障害者保健福祉手帳の交付申請について」
療育手帳
療育手帳は知的障害がある人に交付される手帳です。自治体によって「愛の手帳」「みどりの手帳」「愛護手帳」といった呼び名があります。区分の判定は、児童相談所又は、知的障害者更生相談所で行います。
| 申請窓口 | 各市町村担当課 |
| 有効期限 | なし |
| 区分 | 区分は各自治体によって違いがあり、東京都・神奈川・愛知県などは最重度・重度・中度・軽度まで4区分、兵庫県・大阪府などは重度・中度・軽度の3区分※等級の詳細は、前述の表「知的障害の区分と状態」を参照 |
| 受けられるサービス |
|
参考:愛知県「手帳の交付申請について」
活用できる支援制度
精神障害者保健福祉手帳・療育手帳といった障害者手帳の他にも、どのような制度が活用できるのかみてみましょう。
精神障害を持つ方の支援制度
障害基礎年金
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
- 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要。
障害厚生年金
次の1~3のすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
- 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合がある。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要。
<参考>日本年金機構
「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
自立支援医療制度(精神通院医療)
精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担額を軽減する制度。通常3割負担が1割負担になる。入院治療は対象外。
特別障害者手当
日常生活において、常に特別な介護を必要とする重度の障害がある20歳以上の在宅の人を対象に支給される。
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害があって、常に介護が必要な20歳未満の在宅の人を対象に支給される。
特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害(障害基礎年金1、2級程度)があって、在宅で生活する20歳未満の児童を養育している人に支給される。
児童扶養手当
母子家庭、父子家庭で、所得制限等の条件を満たした場合支給される。児童が18歳までが対象だが、一定の障害がある児童を養育している場合は20歳まで。
知的障害を持つ方の支援制度
障害基礎年金
知的障害者は18歳までに障害の診断を受けている前提のため、初診日・保険料納付の要件については基本、除外され、支給額は障害の状態によって決定されます。
その他、精神障害同様に特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・児童扶養手当も支給されます。
就労支援について

就労に関する支援については、基本的には障害種別による違いはありません。個人の障害の状態やニーズに応じて、以下のような様々な支援事業所があります。
ハローワーク
障害についての知識をもつ担当者が、就職先の情報提供や相談に対応。職業訓練の実施やトライアル雇用の紹介も行う。
障害者就業・生活センター
就労面…就職活動支援・職場定着支援・関係機関との連絡調整等を行う。
生活面…日常生活に関する助言(金銭管理、住居、年金等)や関係機関との連絡調整等を行う。
障害者職業センター
障害がある人の職業リハビリテーションを行う。職業相談・職業評価・職業訓練・職場定着支援等。
就労継続支援A型事業所
「一般企業での雇用が困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な人」で65歳未満の人を対象に、雇用契約を結ぶもの。最低賃金が保証される。
就労継続支援B型事業所
障害や病気などで一般就労が難しい方を対象として、雇用契約は結ばずに就労の機会を提供。作業内容や時間に応じて、工賃(給与相当)が支払われる。
雇用契約がないためA型に比べて工賃は低めだが、日数・時間ともに無理せず自分のペースでゆっくり利用できるのが特徴。
参考:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
精神・知的障害をお持ちの方の「働きたい」を応援します!
就労センターでは、現在までに700名以上の方々が利用され、そのうち60%以上が精神障害や発達障害をお持ちの方です。
「対人関係が苦手」「静かな環境で作業がしたい」といった方のために、個室スペースを整えており、週1回半日からの通所にも対応していますので、ご自分のペースで安心してご利用いただけます。
また、パソコン作業や様々な軽作業の中から、自分にあった作業に取り組んでいただくことで、作業時間に応じて工賃をお支払いしております。(※収入例:月額42,000~52,000円)
就労継続支援B型事業所の利用をご検討中の方は、是非、就労センターまでご相談ください。

まとめ
本記事では精神障害と知的障害の症状や特性の違い、制度についてみてきました。
支援制度においては、精神障害・知的障害という障害の違いよりも、それぞれ障害の重さによる違いの方が大きいようです。
障害者手帳の所持には抵抗がある方もいると思いますが、メリットも多々ありますので、活用されてみてはいかがでしょうか。また、障害年金は、細かい規定がありますので、詳細を知りたい方は最寄りの年金事務所またはお住まいの市町村福祉課にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。

障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターにて、精神障害や発達障害などをかかえる方に対し社会適応訓練(SST)や創作活動などを通じた支援に精神保健福祉士・社会福祉士として約10年間従事。その知識・経験を活かし、障害福祉分野における啓蒙活動に取り組んでいる。

2014年に行政書士資格取得後、行政書士法人にて研鑽を積み、2016年から障害福祉分野に注力。福祉事業所には欠かせない都道府県・市町村への各種申請件数は100件以上。
また、福祉施策調査を実施し、障害福祉事業所に対し、運営提言も行っている。「行政書士ありもと法律事務所」の代表行政書士でもある。